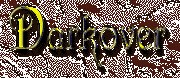1930年6月3日
マリオン・ジマー・ブラッドリー、アメリカはニューヨーク州オールバニに生まれる。
子供の頃の夢はオペラ歌手になることだったが、健康上の理由から断念。しかしこの時のオペラへの傾倒の影響はのちの彼女の作品の随所にあらわれることになる。
1941年
11歳の時、読んでいた小説に影響されてノートに小説を書き始める。(この辺のノリは日本のアニメ・マンガファンとあまり変わらない(^^))
1946〜1948年
16歳頃から、当時のSFやファンタジーに影響されはじめ、17.8歳の時にはノートに長編ファンタジー小説を書き止めていた。だが、それはだらだらと書きたいように書いただけの作品とはいいがたかったものであったらしい(これも、この歳のアニメ・マンガファンにありがち(^^))
だが、この『王と剣』という作品こそが、のちのベストセラー作家M.Z.ブラッドリーの出発点であり、わけても、7つのテレパスカーストに支配されたこの架空世界の物語は、ダーコーヴァ年代記シリーズの設定上の礎となっているのだ!
すでに彼女は当時、この作品を雑誌社の編集者の意見を元に改訂、物語を整理し、設定に手を加え、主人公の名をルー・オルトン、そして舞台を赤き太陽を持つ惑星『ダーコーヴァ』と変え、書き替えている。
そう、まさにこの時から『惑星ダーコーヴァ』と言う存在が彼女の中に生まれたのだ!
1949年
鉄道員ロバート・A・ブラッドリーと結婚(^^)
彼女の作家名はこのだんなさんの姓なんだね。
1954年
「The Door Through Space」(「時空の扉を抜けて」)
1957年
「Falcons of Narabedla」(「ナラベドラの鷹」)
「宇宙の秘密の扉」と「ナラベドラの鷹元」。日本ではダーコーヴァの外伝として文庫に収録されていることからわかるように、ダーコーヴァシリーズと共通の設定が多い。でもこれはダーコーヴァと同じく彼女の試作長編『王と剣』からひっぱってきている設定が多いせいなんだけど、この2編に続いて、『王と剣』改訂版『オルドーンの剣』を発表しようともくろむ!が、しかし掲載紙の廃刊という事件が起き、世に「ダーコーヴァ」の名が出るのは後年にゆずることとなってしまうのだ。
1958年
『The Planet Savers』(「惑星救出計画」)
そして、そしてついにダーコーヴァの名が初めて世にでることに!
きっかけは「宇宙の秘密の扉」がエースブックスの編集者ウォルハイムの目に止まったこと。彼に作品を依頼されたブラッドリーはまたも苦し紛れに(いや、だってそんな気が…(^^;))、『王と剣』から、7つのテレパスカーストを、赤い太陽をそして、ダーコーヴァという名を持ってきた!
それがまさか、このシリーズを死ぬまで書き続ける羽目になろうとは、ブラッドリー本人もまだこの時は知るよしもないのだった・・・・。
1962年
『The Sword of Aldones』(「オルドーンの剣」)
で、The Planet Savers のペーパーバック版発行にあたり、ダブルブック形式(前と後ろから違う作品が始まる)での刊行のためにブラッドリーは同時収録作品を出版社に提出することになる。そこで浮上したのが「オルドーンの剣」。
ずーーーーっと、あたため続けた「オルドーンの剣」を発表できて、彼女的には、もうダーコーヴァはこれで気が済んでしまっていた可能性大(^^;)
だが、なんの運命のいたずらか、「オルドーンの剣」はその年のネビュラ賞候補に!
ブラッドリーは同じ「ダーコーヴァ」の設定を使って、他にも作品を書くことになってしまうのだった。
(しかし、アメリカの人たち、予備知識なくいきなりこの作品読んで、よく話の意味がわかったな・・・(^^;))
1963 ブラッドリー女史はロバート・A・ブラッドリーと離婚。しかし作家としてちょうど名が売れはじめたころなためか、作家としての姓はそのまま使い続けることになる。
1964年
『The Bloody Sun』(「宿命の赤き太陽」)
このころは、まだ駆け出しの作家ということで、手探りしながらこわごわ書いてる感じ。
この「The Bloody Sun」も推理物の色を帯びていて、ダーコーヴァシリーズ中では異色の作品ではあるが、当時流行っていたと思われる「男性主人公の異世界冒険物」「冒険の結果としての賞品としての美女との恋愛」という王道を逸脱していない。この傾向については「The Planet Savers」などの他の初期作品にも見受けられる。
まだ、ホントのブラッドリー色は出てないのだ。
1965年
『Star of Danger』(「はるかなる地球帝国」)
ブラッドリー的にはこれで一応「ダーコーヴァ物」は完結させて、作家として次なるステップに進むためにも、全く違った作品を書くつもりであったらしい。
なのでこの「Star of Danger 」はこれでもかというくらい、綺麗にまとまっているのだ。『そしてふたつの兄弟星はふたたびひとつになったのだ』とかいって、根深いはずのダーコーヴァと地球帝国のあつれきをこの1行で丸めてしまおうという荒技である(笑)。
・・・だが、世間の人気と出版社がそれをゆるしてはくれなかった・・・。こなるともう少年○ャンプの人気連載と同じなのだ。
書かねばならない。
1970年
『The Winds of Darkover』(「炎の神シャーラ」)
「The Winds of Darkover」の本当のタイトルは「The Wings of Darkover」・・・なるほど、話の内容からしても、鍵をにぎるのは機械仕掛けの鳥なわけだから、こっちの方がしっくりくる。
写植のミスで変わってしまったこのタイトル・・・しかし、この間違ったタイトルから、ブラッドリーはダーコーヴァワールドの根源にかかわる設定「魔の風」のインスピレーションを得たというのだから、ホント転んでもただでは起き上がらない方である。
そしていよいよ、「今度こそ、これでダーコーヴァを最後にするぞ!」という、新たなる意気込みをこめて(^^;)、彼女は、初めてチエリを中心とした物語を書くことを思い立つ。
1971年
『The World Wreckers』(「惑星壊滅サービス」)
これにはル・グィンの「闇の左手」の影響によるものが大きいのは周知の事実。が、彼女的にはずっと書きたかった物語だったはずで、ただ、それが世間に受け入れられるのがこわくて書けなかった・・・というのが正しいんではないかな、とういうのが私の見解(^^)
ダーコーヴァの初期作品が他の男性作家の異境冒険物の展開を意識しているのを見てもわかるように、デビューして仕事が軌道に乗りはじめたばかりの作家というのは、やはり作品上の「冒険」をやるには勇気がいるもの。それを「こういう作品をかいても世間は受け入れてくれるのよ」という意味で、ル・グィンのこの作品はブラッドリーの背中を押してくれたんじゃないかな、という気がするのだ。
濃いめの精神描写、性描写などが続出していて、そういう意味では初めてのブラッドリーがブラッドリーらしい作品と言えるかもしれない。
そして、これもこれでラストのつもりで書いていただけあって「Star of Danger 」と同じく、かなり強引にきれいにまとまめてしまっている。・・・ここで、このラスト通り、ダーコーヴァ人の心が深層意識でもきれいにひとつにまとまっていたらレジスも晩年あんなに苦労することなかっただろうに・・・。
―――ところで、その後ケラルはどうなったんだろう・・・・。
1972年
『Darkover Landfall』(「ダーコーヴァ不時着」)
「The World Wreckers」でダーコーヴァを今度こそ、最後にするつもりだったブラッドリー。しかし編集者の「終わりを書いたんだから、最初も書かなきゃあ」という甘言にのせられて、しかたなく「Darkover Landfall」を書き上げる。だが、この時、読者にダーコーヴァ物であることをアピールするために、タイトルにダーコーヴァの文字を入れてくれと編集者に言われたことが、ブラッドリーの意識を変えた。
彼女はここではじめて客観的に自分の作品を人気シリーズとして捕え、さらにこのシリーズの持つ可能性に改めて気付いたのである。
そして、彼女のダーコーヴァシリーズへの取り組み方はそれまでの編集者に言われて書く受動的なものから、能動的なものに変化する。
ここから、本当の意味でのブラッドリーのダーコーヴァシリーズが始まるのだ!
1974年
『The Spell Sword』(「カリスタの石」)
まだ、この辺ではそれまでの「異世界冒険物」「冒険の果ての報償としての美女との恋愛」というスタンスは崩されていない。
だが・・・
1975年
『The Heritage of Hastur』(「ハスターの後継者」)
おそるおそるとではあるけれど、ようやっと彼女の「ホンネ」がこの辺から出てくる感じの作品(^^)。ブラッドリーがこの「ハスターの後継者」を描くきっかけになったという手紙をかいた、J・リヒテンバーグはえらい!
ブラッドリーはこの方の「オルドーンの剣」の設定概要に関する手紙を読んで、「レジスはこんなこと言わない、ルーはこんなこといわない」と燃えて「ハスターの後継者」を書き上げた。しかし「ストーリー」が違うんじゃなくてキャラなんかい!とおもわず突っ込みを入れたくなるのは私だけか?!(笑)
(元々「ハスターの後継者」はブラッドリーの身内で回し読みされていた「傲慢」というタイトルの話が元になっているらしいんだけど、なんかこの人この手の身内でしかしらない、あるいは自分がノートに描き止めただけの隠し球的な作品はまだいっぱいあるんじゃないかって気がする〜。)
その後、彼女がいわばおそるおそるともいえる形で、自身の濃い趣味性を反映したこの作品は予想外にうけて、SF界どころか一般書籍界まで巻き込むベストセラーに!
そこで、彼女は気付いた・・・「そうか、わたしはこの路線で自分に正直に描いてもいいのね!」てな感じでしょうか?次の「砕けた鎖」から、いきなり趣味全開、本当の意味でのブラッドリーらしいブラッドリー作品が読めるのはこの辺からなのです。
1976年
『TheShattered Chain1』(「ドライ・タウンの虜囚」「ヘラーズの冬」)
そして、ダーコーヴァシリーズ中、もっとも濃くブラッドリーの趣味的な部分を反映していると思われるのがこの作品、「禁断の塔」。
アメリカのダーコーヴァファンサイトの人気投票では「ハスターの後継者」とともにシリーズ中人気No.1をあらそう名作です。
1977年
『The Forbidden Tower』(「禁断の塔」)
この名作「禁断の塔」の発表後、前々からファンの要望の強かった「混沌の時代」物がいよいよ世に姿を表します。
しかし、ブラッドリー自身が「ダーコーヴァの真髄は地球帝国とダーコーヴァの文化衝突に有り、それがないダーコーヴァはそのへんのSFとかわらなくなってしまう」と語っているように、「混沌の時代」ものはストーリー的にも魅力があり、ダーコーヴァ世界の成り立ちを知るうえでファンには興味深い作品群ではあっても、ダーコーヴァシリーズとしての本当の輝きは無いような気がするのです。
1978年
『Stormqueen!』(「ストームクィーン」)
1980年
『Two to Conquer』(「キルガードの狼」)
「ハスターの後継者」を書き上げた当時から、この作品と他作品との矛盾がまことしやかにあげつらわれ、これを補正するためにブラッドリーは「オルドーンの剣」を書き直すのではないかという話・・・「書き直したものが読みたい」というファンの希望はずっと水面下にあったらしい・・・そしてついにブラッドリーが根負けして書き上げたのが、この作品・・・いっそ、「惑星壊滅サービス」とかも書き直してくれと思うのは私だけか(笑)
1981年
『Sharra's Exile』(「シャーラ追放」<オルドーンの剣改訂版>未邦訳
1982年
『Hawkmistress!』(「ホークミストレス」)
1983年
『Thendara House』(「ゼンダラの館」・未邦訳)
1984年
『City of Sorcery』(「魔法の都」・未邦訳)
1983年には、あの大ベストセラー「アヴァロンの霧」も発表され、いよいよ油の乗ってきた感のあるブラッドリー作品・・・だが、この時期にブラッドリーは突然、脳卒中でたおれる。幸い助かるが、以後体をいたわりながらの執筆を余儀なくされるのである。
1986年、この年、日本でもいよいよダーコーヴァシリーズが刊行されはじめるが、現在「キルガードの狼」以降の刊行のめどがついていないのは皆さんもご承知の通りである。
1989年
『The Heirs of Hammerfell』(「ハンマーフェルの後継ぎ」未邦訳)
アメリカのサイトをみるとシリーズ最悪の駄作との酷評・・・前作とのブランクがある分まだ、筆が乗ってないんじゃないかな?
1993年
『Rediscovery』(「再発見」・未邦訳)
これまた、酷評・・・。地球人がはじめてダーコーヴァにやってきた時の物語。なんといっても議論を呼んだのは、とにかく他作品との設定上の食い違いが多すぎること!カーミアック・アルダランがこの頃から登場してるということは・・・「ハスターの後継者」で100才越えちゃうじゃん!みたいな(^^;) でも.一方ではダーコーヴァの主要都市が赤道付近にあるらしいなどの真新しい発見も・・・。
その後、A・M・Barnesという人が「Sharra's Exile」のサブキャラ、マルジャのキャラクターを膨らませてくれたのがきっかけで、描かないといっていた「惑星壊滅サービス」以後のダーコーヴァの姿がついに描かれることになるのだ!
1996年
『Exile's Song』(「放浪の歌」・未邦訳)
1997年
『The Shadow Matrix』(「シャドウマトリクス」・未邦訳)
1998年
『Traitor's Sun』(「裏切りの太陽」・未邦訳)
1999年9月21日
心臓発作を起こし、入院。
同年9月25日
マリオン・ジマー・ブラッドリー死去。享年69才。
ダーコーヴァというすばらしい世界をはじめ、数々の作品で読者を魅了した女流作家は、心の中に温めていた作品やエピソード、キャラたちと共にあの世に旅立ってしまった。
心よりのご冥福をお祈りします(;_;)。
・・・そして、遺作はダーコーヴァの新作という話なんだけど、果たして刊行は・・・??

※このページのダーコーヴァ作品に関するコメントは、日本版ダーコーヴァの解説ページや原作ペーパーバッグのブラッドリーのコメントなどを元に、管理人が独自の感想やつっこみを交えて構成したものです。
もしかしたら勘違いなどもあるかもしれませんが、その場合は遠慮なく御指摘下さい。 |